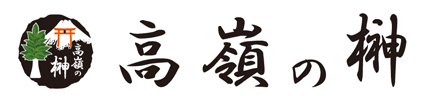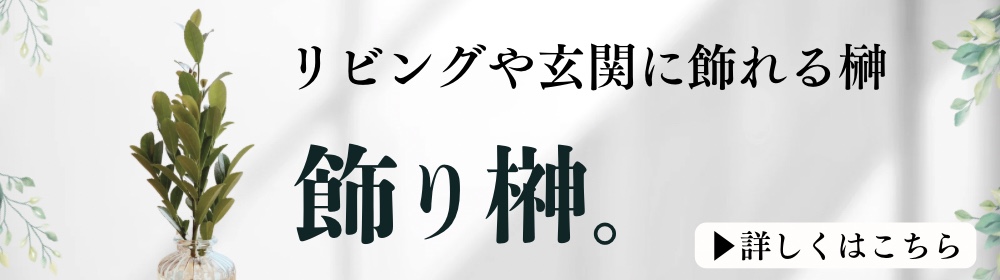毎月の榊は「月の区切りに感謝を捧げる」ためです。基本は1日・15日。忘れたら気づいた日に丁寧に。作法・地域差・長持ちのコツまで一気に解決します。
榊を1日・15日に替えるのはなぜ?神道の由来と地域差

1日・15日は朔日と十五日、月の区切りで感謝を捧げる日である
1日・15日は月の始まりと中日に、日常の無事を言上する日です。
朔日=新月の頃。十五日=満月の頃(望)。満ち切って、やがて欠けへ転じる節目です。自然暦に基づく感謝です。※満月は天文学的に14〜16日頃になる年もあります。
「榊を1日と15日に交換するのはなぜ?」への答えは、月の営みに合わせた祈りの節目です。
あなたの暮らしも、このリズムで整います。
神社の月次祭が家庭の神棚にも広まったのが習慣化の背景である
神社では毎月の恒例祭(多くは「月次祭/つきなみさい」と称します)で平安を祈ります。
この慣習が家庭の神棚へ広がり、榊を整える日となりました。
注:本来「月次祭」は古典的には6月・12月の大祭を指す言い方もありますが、現代では各神社が毎月行う恒例の祭祀を広く「月次祭」と呼ぶことが一般的です。
榊農家の現場でも、1日・15日の需要が突出します。
「榊を1日と15日に交換する理由」は、神社祭祀の家庭化と覚えてください。
月次祭の中身と参列のすすめ
月次祭は多くの神社で毎月の恒例祭として営まれ、神社により月1〜2回のところもあります。
基本はお供え(神饌)と祝詞の奏上。細部は地域・神社で少しずつ異なります。
- 氏子や参拝者が参列・見学できる神社もあります。気軽に社務所へ。
- 祭典後にお下がりをいただく直会(なおらい=神と人が恵みを共にする所作)を行う社もあり、食べ物や水が神さまの恵みであることを思い起こす良い機会になります。
- 1日・15日に参拝の予定を合わせ、家庭の神棚の節目とリズムを揃えるのも気持ちよく続きます。
旧暦から新暦への移行で日付はずれたが、区切り日として定着している
明治の改暦(1872年の布告により1873年から新暦採用)で、朔日と十五日は新暦日付とずれました。
それでも区切り日として「1日・15日」が定着しています。
「月の区切りに感謝する」という本質は変わりません。
迷ったら、この本質に立ち返れば大丈夫です。
氏神や地域により「毎週」「月末」など違いがあるのも正しい
地域により「毎週月曜」「月末」など多様です。
氏神や崇敬神社の案内に従えば、それが正解です。(現代では「氏神」は住む土地を守る身近な神社を指す言い方として広く用いられています)
暮らしに合う頻度で続けることがいちばん尊いのです。
肩の力を抜いて、あなたのリズムを整えましょう。
交換頻度とタイミング:基本は1日・15日、枯れたら都度が正解

原則は1日・15日だが、榊が弱ったら日を待たずに替える
基本は1日・15日。しかし葉が垂れたら都度替えます。
清浄が第一。「榊 1日 15日 なぜ?」よりも状態優先で。
水が濁ったら、それも替え時のサインです。
迷ったら「今整える」。それで十分です。
朝の清浄な時間に行うのが一般的だが、都合の良い時で差し支えない
一般には朝の拝礼前が最適です。空気が澄んでいます。
ただし、無理は禁物。あなたの都合でかまいません。
夕方になっても、丁寧に整えれば心は届きます。
「忘れたら」も同様。気づいた時に整えましょう。
忙しい家庭は「週1」や「吉日」など一定のリズムで続ければよい
続けやすさが要です。たとえば次のリズムも可です。
– 週に一度、同じ曜日の朝に
– 六曜や選日(暦注。天赦日・一粒万倍日など)の吉日に
– 給料日や家族の予定に合わせる
– 毎月のあなたの誕生日に、健康・安全と親やご先祖への感謝を伝える
– 月末に「今月も無事に過ごせました」と振り返る
続く仕組みが、祈りを暮らしに根づかせます。
無理のない約束を自分と交わしましょう。
月に一度の「自宅版・月次祭」をつくる
結論:月に一度だけ「いつもより丁寧に」向き合う日を設けると、無理なく続きます。
やり方はシンプルで十分です。
- 季節の花を一輪添える
- いつもと違うお供えを少し(旬の果物やお茶など)
- 神棚まわりの整理整頓と拭き掃除をする
毎月の節目をつくると、暮らしにリズムとメリハリが生まれます。
「神棚と自分のメンテナンス日」として、心が整います。
氏神や崇敬神社の案内がある場合はそれに合わせる
氏神=住む土地を守る神社です(厳密には産土神・鎮守などの呼び分けもありますが、日常的には最寄りの守護神社を指すことが一般的)。掲示や頒布物を確認。
祭事に合わせると、地域と祈りがつながります。
迷ったら社務所に一言相談を。きっと力になってくれます。
地元に学ぶ姿勢が、いちばんの近道です。
忘れたらどうする?気づいた時に丁寧に、お詫びの詞を添える

忘れても気づいた時点で整えれば問題はない
「忘れたら」大丈夫。気づいた時が良い時です。
慌てず整え、心を向ければ充分に届きます。
自分を責めず、次に活かしましょう。祈りは続けるほど育ちます。
「本日まで失念しておりました」と一言詫びて感謝を伝える
おすすめの詞
- 本日まで失念しておりました。
- 心を改め、感謝をおささげします。
- 今後も見守りください。
日付がずれても誠は伝わります。
「榊を1日と15日に交換する習慣」の核心は真心です。
日付をずらしても神様には心が届くため差し支えない
翌日や翌々日でも差し支えありません。
生活に根づく形で続けましょう。
「忘れたら」は工夫で防げます。
次項のリマインダー設定が役立ちます。
繰り返し防止はカレンダーやスマホのリマインダーが有効
実践の工夫
- 月1・15日の繰り返し通知
- 家族カレンダーに共有
- 榊の水替え専用の付箋を神棚に
小さな仕組みが、習慣を支えます。あなたの暮らしに合う方法で。
まとめ:今日から「1日・15日」を感謝の習慣に。忘れたら気づいた日に整えよう

– 1日・15日は月の区切りに感謝を捧げる日
– 枯れたら日を待たずに替えるのが正解
– 「忘れたら」気づいた時に丁寧に整える
– 月に一度の「自宅版・月次祭」で、暮らしにリズムとメリハリを
次の一歩
– 今すぐスマホに1日・15日の通知を設定
– 榊・米塩水の補充を用意
– 定期便で「続く仕組み」を整える
「榊を1日と15日に交換するのはなぜ?」の答えは、感謝の節目作り。あなたの暮らしに、静かな祈りの灯をともしてください。
出典
– 神社本庁「神棚のまつり方」「参拝の作法」
– 國學院大學デジタルミュージアム「月次祭」「朔日」「氏神」
– 神宮司庁(伊勢神宮)「朔日参り」紹介頁
– 国立天文台「暦の基礎知識」「明治改暦と新暦採用」