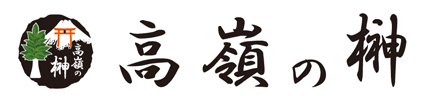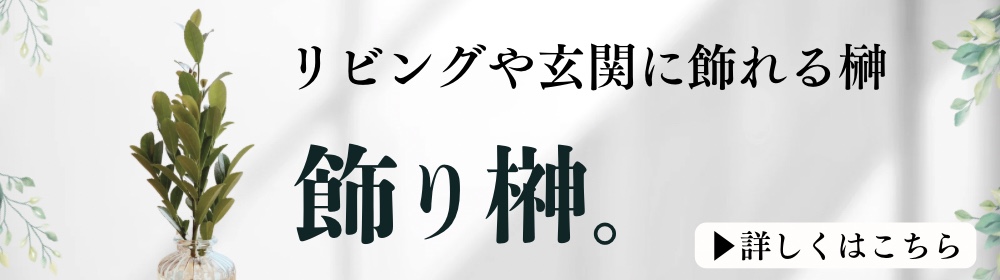榊に毒性はあるのか? シキミと間違えたらどうするのか?
本記事は、榊とシキミ(樒)の違い、家庭での安全な扱い方、誤食が疑われる際の行動指針を、実務目線で整理します。正しい知識を持てば、日々の神拝を安心して続けられます。
榊とは?——基本情報と主な種類

榊(さかき)は、日本の神棚や神事で広く用いられる常緑の小高木です。園芸・流通上は次の二種が中心です。
- 本榊(サカキ:Cleyera japonica)……厚みとつやのある葉。葉縁は滑らかな全縁。
- ヒサカキ(Eurya japonica)……やや小葉でマットな質感。葉縁に細かな鋸歯。
用途や地域の慣習に応じて使い分けられますが、どちらも家庭で扱いやすい常緑枝物です。
榊に毒性はあるのか?——安全性の考え方

結論として、榊そのものが強い毒性植物として扱われることは一般的ではありません。神棚用として広く流通し、通常の飾り方・触れ方で健康被害が問題化する事例は稀です。
一方で、観葉植物全般に共通する注意として、大量摂取は消化器症状を招き得ること、個人差によって接触皮膚炎などが起こり得ることは念頭に置きましょう。
安全側に倒すなら、次を徹底します。
- 幼児・ペットの手の届かない高所に設置する
- 交換・剪定時の切り枝や枯葉を放置しない
- 作業時は手袋着用・手洗いを基本にする
シキミ(樒)は強い毒性を持つ別種——混同防止が最重要

シキミ(樒、Illicium anisatum)は有毒植物で、神経毒性を示す成分(アニサチン等)を含みます。仏事で用いられることがある一方、中国産の八角(トウシキミ:Illicium verum)との混同事故が国内外で報告されており、取り扱いには最大限の注意が必要です。
榊とシキミの見分け方(実物・用途・果実でチェック)
見た目が似る場面がありますが、次の観点で見分けられます。
- 葉
- 榊:厚くつやがあり、葉縁は全縁(滑らか)
- シキミ:葉も基本は全縁だが、葉が波打って見えることがある。葉や枝を揉むと強い芳香
- 花
- 榊:小さな白〜黄白の花(初夏)
- シキミ:淡黄〜黄白の花(春、花被片が多く星状に見えやすい)
- 果実
- 榊:小さな黒いベリー状
- シキミ:星型の木質果(八角に酷似・有毒)
- 文化的用途
- 榊:神道(神棚・玉串)
- シキミ:仏事(墓前・仏壇、抹香原料)
不安がある場合は、専門店での購入・名称ラベルの徹底・混在保管の回避で誤用リスクを確実に下げられます。
子ども・ペットがいる家庭の安全運用

日常の飾り方で大きな危険は想定されませんが、安心のために次を心がけてください。
- 設置:神棚は高所かつ固定し、落下対策を行う
- 管理:交換・剪定時はその場で回収・清掃。床面やケージ周りに葉を残さない
- 保管:榊・シキミ・その他の枝物は名称ラベルを付け、置き場所を分ける
- 屋外:シキミが身近にある地域では、星型の実を持ち込まない・触らせないルールを家族で共有
誤食・誤飲時の対処
榊(サカキ)と思われるものを少量口にした
– まず口をすすぐ
– 少量で無症状なら経過観察でよいことが多い
– 大量摂取、反復する嘔吐・腹痛、発疹や呼吸症状などがあれば受診する
シキミ(樒)または不明だがシキミの可能性がある
– 直ちに医療機関へ(救急外来)
– 自己判断で嘔吐は誘発しない
– 受診時は現物や写真、摂取量・時刻、症状を伝えると診療がスムーズ
家族が判断に迷う場合は、日本中毒情報センター(中毒110番)に相談すると安心です(24時間対応)。
よくある誤解と補足
- 「榊=完全に安全」ではない:非毒性扱いでも、大量摂取や個人差で消化器症状等は理論上起こり得ます。
- シキミは強毒:星型の果実・強い芳香を手掛かりに、八角や榊との混同を避けることが肝要です。
- 迷ったときは、「口に入れない・混在させない・専門店で調達」の三原則でリスクを最小化できます。
まとめ——正しく見分けて、無理のない安全運用を
- 榊(サカキ)は通常利用で強い毒性は一般的ではないが、口に入れない配置と日々の管理を基本に。
- シキミ(樒)は強い毒性を持つ別種。星型の果実・強い芳香・仏事用途を手掛かりに混同を回避。
- 誤食が疑わしいときは、早めに医療機関/中毒110番へ相談。
- 品質・安心を優先するなら、信頼できる専門店や定期便で本榊を入手するのが確実です。
参考情報(出典)
- 厚生労働省「有毒植物による食中毒に注意しましょう」 oai_citation:0‡厚生労働省
- 日本中毒情報センター「中毒110番・電話サービス」(大阪 072-727-2499/つくば 029-852-9999) oai_citation:1‡公益財団法人 日本中毒情報センター
- 東京都保健医療局「有毒植物について(シキミ、症状・毒成分の説明)」 oai_citation:2‡hokeniryo1.metro.tokyo.lg.jp
- 国立医薬品食品衛生研究所 健康危機管理研究センター「シキミの実による食中毒事例(アニサチン検出)」 oai_citation:3‡H・CRISIS
- 林野庁 関東森林管理局「危険な動植物に注意(シキミに関する注意喚起)」 oai_citation:4‡林業ネットワーク
- 農林水産省「野菜・山菜とそれに似た有毒植物」 oai_citation:5‡農林水産省
- 厚生労働省 通知資料「有毒植物の誤食による食中毒防止の徹底について(2025)」 oai_citation:6‡厚生労働省
※本記事は一般的な情報整理です。緊急時は必ず医療機関または中毒110番の指示に従ってください。