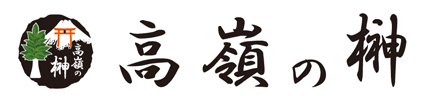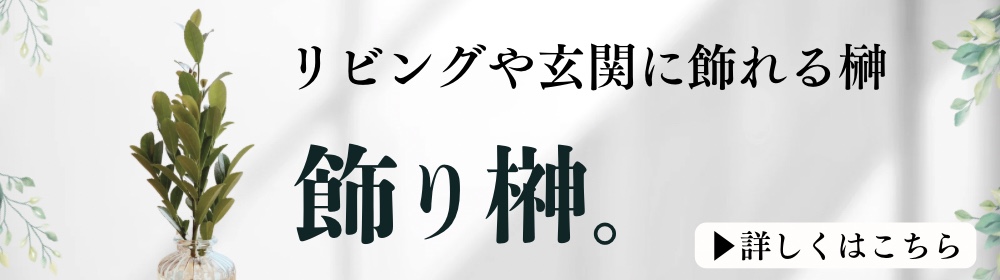仏壇に何を供えるか迷う方へ。結論は「ヒサカキは可、シキミは地域次第、本榊は原則不可」。理由と選び方、作法まで一度でわかります。
結論と基礎知識:仏壇にはヒサカキ可、シキミは地域次第、本榊は原則不可

ヒサカキは仏壇供えとして東日本で広く用いられる
結論として、ヒサカキは仏壇で広く許容されています。特に東日本では標準的な供葉として根づいています。迷ったら第一候補です。
– 植物名:ヒサカキ(姫榊/学名 Eurya japonica、ヒサカキ属)。小葉で扱いやすく、流通も安定
– 地域の呼び名:地域差が大きく、シャシャキ・ビシャコ・ヒサギなど多様な呼称があります(サカキに似た別種です)
※豆知識:常緑の枝物(供葉)を供えるのは、常に青々とした葉が「清浄」「変わらぬ敬意」を象徴すると考えられてきたためです。
シキミは仏事伝統の供葉で西日本中心、地域慣習に従う
シキミ(樒、学名 Illicium anisatum)は仏事ゆかりの木。西日本では仏壇・お墓に定着しています。地域・宗派差が大きいので寺院確認が安心です。
– 強い香りと長持ちが特長。全草に強い毒性があり、誤食・ペット対策に注意(料理用スパイスの八角〈スターアニス〉と混同厳禁)

本榊は神棚用の供葉で仏壇には基本的に用いない
本榊(サカキ、榊/学名 Cleyera japonica)は神道の供葉。仏壇は別系統の供養なので原則避けます。神棚には本榊、仏壇にはヒサカキやシキミが基本です。
– 見分けのコツ:サカキは葉縁がほぼ全縁(ギザギザが少ない)、ヒサカキは小葉で葉縁に細かな鋸歯が出やすい。地域で混同があるため、標札や販売表示を必ず確認
最終判断は菩提寺や地域の慣習を確認するのが安心
あなたの家の作法は、菩提寺と地域の習わしが基準です。迷いを手放す最短は「電話で一言確認」。きっと安心が続きます。
– 確認先:菩提寺の住職・檀家総代・地域の仏具店
用語メモ:供葉=供養に供える常緑の枝物/本榊=神道の榊(サカキ)/花立=仏壇の花器
仏花・墓花・供花の呼び分け(知っておくと注文がスムーズ)
仏花はお仏壇に供える花の束、墓花はお墓に供える一対の花、供花は葬儀や法要会場に飾る花全般を指すことが多いです。呼び分けは地域で混同もあるため、買うときは「仏壇用」「お墓用」など用途をはっきり伝えると行き違いが減ります。
お花を供える意味(心が整います)
花を供えるのは、故人や先祖への感謝を形にするため。生花がやがて枯れる姿に、無常といのちの尊さを学ぶ意味もあります。毎日の拝礼で心が静まり、悲しみが少しずつ癒えていきます。あなたのペースで大丈夫です。
仏壇での正しい供え方・作法

花立は一対を左右対称にし、ご本尊を隠さない丈に整える
花立は左右一対が基本。ご本尊が隠れない肩の高さにそろえます。枝は正面に葉が向くよう角度を整えましょう。
– 目安:本尊の顔が見える高さ/左右のバランス/枝の向きと広がり
– 補足:宗派や仏壇の形式により一対でない配置もあります(菩提寺の指示を優先)
交換は1〜2週間が目安で、法要・お盆・彼岸は新しいものを供える
水が澄まず香りが落ちたら替え時。日常は1〜2週間が目安です。法要やお盆・彼岸は新しい枝で迎えましょう。
– 交換サイン:葉の艶が鈍る/切り口が褐変/水に匂い
棘物・強香・過度に長い枝は避け、清潔な水と器を保つ
トゲのある枝や刺激臭の強い植物は避けます。水は清潔第一。花立はぬめりを落とし、雑菌を抑えましょう。
– 避けたい例:バラのトゲ/極端に長い枝/強い人工香
仏花の形・本数・色の基本(花束を作る場合)
仏壇に飾る仏花(花束)は一対で左右対称が基本です。本数は奇数(3・5・7本など)が目安。形は上部をやや細く、下にボリュームを置く「ひし形」にまとめると美しく収まります。配色は白・黄・紫を中心に、必要に応じて赤やピンクを加えます。四十九日までは白基調で静かに整えると安心です。近年は単体仕様の仏壇もあるため、住まいの事情に合わせて無理なく整えましょう。
– 地域差メモ:西日本の一部では花束の後ろに葉ものを添える風習があり、関東・北陸以北は花だけで束ねるのが主流。ただし、ヒサカキの枝を単独で花立に供える慣習は東日本でも広く見られます。
ヒサカキの選び方と長持ちのコツ

良品は葉の艶と濃緑、切り口の白さ、虫食いの少なさで見分ける
ヒサカキは葉の艶が命。濃い緑で張りがあり、切り口が白く新鮮な枝を選びます。虫食いと折れは避けましょう。
– 選別軸:艶・色・張り・切り口の白さ・枝の締まり
下処理は余分な葉を落とし斜め切り、必要に応じて湯揚げを行う
水に浸かる葉は落とし、茎は斜めに新切り。萎れ気味なら湯揚げで導水を助けます。台所でも簡単にできます。
– 湯揚げ:切り口を熱湯10〜20秒→すぐ水へ→活ける
水替えは毎日〜隔日、直射日光とエアコン風を避け花器を洗う
水は毎日〜隔日で新鮮に。直射日光・エアコン風は乾燥のもと。花器はスポンジでこまめに洗いましょう。
– 併用技:切り戻し1cm/防腐剤(延命剤)少量/水温は常温
枯れた後は感謝して包み適切に処分し、地域の作法に従う
供え終えた枝は紙に包み、感謝を込めて処分。自治体の分別や地域の作法に合わせ、静かに扱いましょう。
– 処分例:可燃ごみ分別/寺の古葉回収があれば利用
入手方法・サイズ・価格と代替案

入手は仏具店・花屋・スーパー仏花コーナー・通販が安定
日々の仏壇用ヒサカキは身近で手に入ります。品質は店の回転率と保管で変わります。顔なじみの店を作ると安心です。
– 入手先:仏具店/花屋/スーパー仏花/通販(定期便が便利)
サイズは小型仏壇20〜30cm、中大型30〜40cmを基準に調整する
仏壇サイズで丈を決めます。小型は20〜30cm、中大型は30〜40cmが目安。ご本尊の顔が見える高さに。
– 確認:花立の深さ/本尊の位置/棚のクリアランス
価格は季節で変動し1束数百円が目安で、継続コストを把握する
相場は1束数百円。お盆や年末は高騰しやすいです。月替え2〜4束で、年間コストを見積っておくと楽です。
– 節約術:定期便/地場産の利用/長持ちケアの徹底
代替はシキミや常緑の造花・プリザ、急ぎは庭木も礼を尽くす
地域がシキミならそちらで。管理重視なら造花・プリザも選択肢。急ぎは庭木でも、清潔に整えて丁寧に。
– 代替候補:シキミ/造花の常緑枝(ヒサカキ・シキミ風)/プリザ常緑/常緑低木の枝
– 補足:造花・プリザは清潔で手入れ軽減の利点があります。生花を供える大切さもあるので、時折は生花で季節を感じるのも素敵です。
【ご案内】高嶺の榊 定期便申し込み
忙しい方に。高嶺の榊は農家直送で鮮度長持ち。仏壇サイズに合わせて選べ、交換時期に自動で届きます。
仏花(花)の選び方と避けたい例(葉もの以外も知っておくと安心)

長持ちしやすい定番と季節の楽しみ
キクはたいへん長持ちで扱いやすく、香りは邪気払いとも。カーネーションやスターチスも散りにくく重宝します。ユリは上品ですが強い香りの品種は避け、花粉は外して清潔に。季節の花を少し添えると歳時が感じられます(春はアイリス、夏はジニアやグラジオラス、秋はリンドウ、冬はストックなど)。
不向きな花の目安
花びらが散りやすいもの、強い香り、トゲのある花、毒性が強い植物、つる性の花、縁起を損なうとされるものは避けます。お墓用と兼ねる場合は特に強香や散りやすさに配慮し、使い回しは控える考えもあります。
自分で束ねるときのコツ
花材を3〜7本用意し、水に浸かる葉を外してから、中心を軸に長短をつけて「ひし形」に。左右対称を意識して束ね、茎を少しずらして輪ゴムでやさしく留めると安定します。初心者はキクとスターチスから始めると扱いやすいです。
安全・注意点と法的・倫理面

シキミは全草有毒につき誤食・ペット対策と設置場所に配慮する
シキミは全草有毒です。小さなお子さま・ペットの届かない位置へ。誤食防止の掲示も有効です。
– 対策:高所設置/落葉の掃除/実が付いている場合は落果・誤食防止のため取り除くか高所に設置
宗派と地域差が大きく最終判断は菩提寺・寺院への確認が確実
作法は宗派と地域で変わります。仏壇の供葉は「家の作法」が最優先。僧侶の一言が最良の道しるべです。
– 確認項目:供葉の可否/本数/行事時のしつらえ
山野の無断採取は禁物で、墓地や近隣への配慮と管理を徹底する
山林や公共地の無断採取は違法・迷惑です。所有者の許可を得ましょう。墓地や共同スペースも配慮が必要です。
– マナー:私有地は必ず許可/剪定後の清掃/音と時間帯配慮
花立の安定と匂い・アレルギー対策で家庭内の安全を守る
花立の転倒防止と水のこぼれ対策を。香りや花粉に敏感な方は換気と種類選びで調整しましょう。
– 工夫:重心の低い花立/吸水スポンジ併用/低刺激の枝を選ぶ
まとめ:地域と菩提寺に確認し、適切な葉を選んで今日から整える

結論の再確認です。ヒサカキは仏壇に可、シキミは地域次第、本榊は原則不可。迷ったら菩提寺に相談しましょう。
次の一歩は「花立を整える→ヒサカキを1対で供える」。定期便を使えば、交換の心配も減り日々が整います。
出典:
- 消費者庁「シキミ(樒)による食中毒に注意」
- 神社本庁「神棚のまつり方(榊の供え)」
- 浄土真宗本願寺派・曹洞宗 各公式サイト(家庭の仏事・供花の基本)
- 警察庁・各都道府県警「山菜・樹木等の無断採取は犯罪」