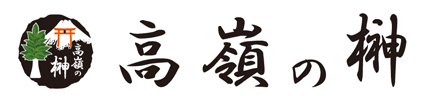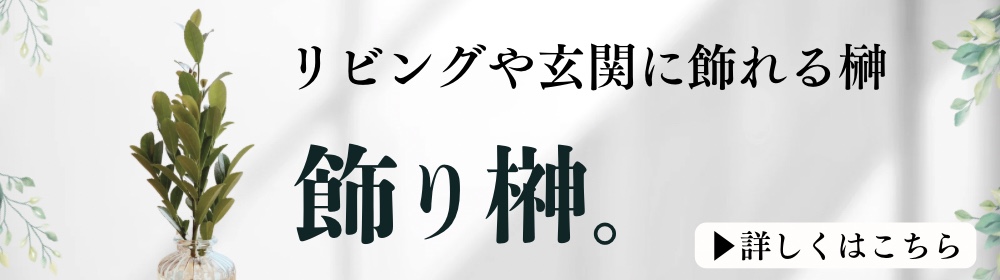榊は素材、玉串は祈りの形です。玉串奉奠と玉串料の要点をシンプルに習得。地鎮祭・神葬祭でも迷わない所作と、榊の調達・保管のコツまで一気に分かります。
榊と玉串の違い・由来:意味と役割を一度で整理

榊は常緑広葉樹で、神事の清浄と境界を象徴します。
榊は艶のある常緑樹。場を清め、俗と聖の境を示します。神籬や榊立に供え、神さまを迎える印になります。
- 種類:サカキ(Cleyera japonica/ツバキ目・サカキ属)。地域によってはヒサカキ(Eurya japonica)を使用します(寒冷地など、サカキの自生が少ない地域で一般的)。
- 役割:清浄・結界・神招きの標識。
- 置き所:神棚左右の榊立(さかきたて)、祭場の標点として使用。
- 手入れ:切り口を新しくし、清水で整えます(斜めに水切り)。
[用語補足]
- 神籬(ひもろぎ):神が一時的に降りる依代(よりしろ)。
- 榊立:神棚に榊を立てる花器(対で用いる)。
玉串は榊に紙垂などを付した捧げ物で、祈りを託します。
玉串は榊に紙垂や麻・木綿を結んだ奉献物。心を託し、神前に丁重に奉ります。
- 構成:榊+紙垂(しで)+麻(または木綿〈ゆう〉)。
- 意味:祈りを可視化した「橋」。敬意と感謝を形で示します。
- 使途:地鎮祭・神前式・神葬祭・年中祭など広く用います。
- 取扱い:根元(柄)を尊び、奉奠時には「根元を神前へ向けて」供えます。
- 備考:地域により榊の代わりに杉枝などで玉串を作ることもあります。
[用語補足]
- 紙垂:雷形の白紙。清浄を表します。
- 木綿(ゆう):神道でいう「木綿」は綿花ではなく、白い布・麻・和紙帯の総称です(誤解されがちなポイント)。
榊は素材、玉串は供え物で、役割は「木」と「祈りの形」です。
榊と玉串の違いは明快。榊は素材の木、玉串は祈念を結んだ供え物で、準備・扱いが変わります。
- 榊:常設・場の清浄化。交換・手入れが要点。
- 玉串:式中の奉献。所作と向きが要点。
- 準備:神社や祭員が用意するのが基本。家庭や会社での神事は事前に神社へ相談を。
- 用語:奉奠(ほうてん)は供える所作のこと。「玉串奉奠(たまぐしほうてん)」が標準表記ですが、案内表記に揺れ(ほうでん)も見られます。
読みは「さかき」「たまぐし」で、由来は神に捧げる意です。
榊は「境の木」に通じ、玉串は「霊威(たま)を宿す捧げ串」と解されます。いずれも神に捧げる敬語的表現です。
- 神籬(ひもろぎ):神が降る依代。
- 地域差:名称・材料に土地の伝承が反映されます。
神話と語源の小話(さらっと知って安心)
- 起源伝承:天照大神の岩戸隠れで、天太玉命(フトダマ)が玉や鏡を付けた「五百津真賢木(いほつのまさかき)」を捧げた故事が、玉串の原像とされます。
- 性格:玉串は神霊の依代(よりしろ)としての性格をもち、そこに祈りを託す道具です。
- 語源諸説:平田篤胤=「玉(たま)を付けた串」説/本居宣長=「手向串(たむけぐし)」転訛説/「たま=魂」説など。
玉串奉奠の基本作法:受け方から二拝二拍手一拝まで

受け取りは右手上・左手下で根元を支え、浅く一礼します。
祭員から受ける際、右手で根元側を上から、左手で下から支え、胸の高さで丁寧に持ちます。
- 受けの礼:軽く会釈して受ける。
- 右手は上から軽く添え、左手は根元下を安定させる。
- 体の中心で静かに保持。受け取り時の向きは場の指示に従えば安心です(後述の奉奠時に根元を神前へ向けます)。
[一口メモ]参進前に手水(てみず)で手口を清める案内があれば従いましょう。
進み出て一礼し、時計回りに回して根元を神前へ向けます。
神前へ進み軽く一礼。玉串案(たまぐしあん/玉串台)の前で姿勢を正し、玉串を時計回りに回して、根元を神前、葉先を自分側に整えます。
- 回す手順:右→手前→左→奥の順に約90度ずつ。
- 流派によっては、いったん根元を自分側にして心中で祈念→時計回りに回して根元を神前へ、という手順もあります。
- 根元を手前から前方へ滑らせて置く。
- 置いたら一歩下がり姿勢を整えます。
奉奠後は二拝二拍手一拝を正しく行い、下がり際も礼を尽くします。
深い拝2回、拍手2回、最後に拝1回。心を静め、所作はゆっくり端正に。
- 拝の角度:目安45度、深く丁寧に。
- 拍手は肩幅で2回、音をそろえる(神葬祭は忍び手=音を立てない。後述)。
- 終えて浅い礼で後退。向きを変えず数歩下がってから戻ります。
[作法の差]出雲大社など、場によって四拍手が定められている場合があります。必ずその場の指示に従えば失礼になりません。
迷ったら祭員の指示に従えば、細部の違いがあっても失礼になりません。
流派や神社で細部が異なります。榊・玉串の扱いに迷ったら、その場の指示を最優先に。
- 回す方向や手順の違いあり。
- 柏手の回数・音量も場に合わせる。
- 動線・立ち位置は案内に従う。
- 用語・読みの揺れ(例:「玉串奉奠(たまぐしほうてん)」)も事前確認を。
シーン別の玉串作法と注意:地鎮祭・神葬祭・神前式・神棚

地鎮祭は施主代表の所作を丁寧に整え、安全祈願を端正に示します。
施主・施工代表の動作が模範です。玉串奉奠は落ち着き、工事安全を心中で短く祈ります。
- 服装:式典相応のフォーマル(現場動線に配慮)。
- 足元が不安定なら小幅で歩く。
- 工事関係者は順序を守る。
神葬祭は柏手を忍び手とし、音や動作を静かに統一します。
神葬祭では音を立てない忍び手が基本。玉串奉奠も静粛に、遺族・司式者の合図に合わせます。
- 表書きや水引は弔事用を選ぶ。
- 黒白・双銀の水引、結び切り(熨斗は付けません)。
- 拝礼は深く、動作は小さく。
神前式は動線と順番を守り、媒酌人と新郎新婦の所作を優先します。
神前結婚式は進行が定型。新郎新婦・媒酌人が先、親族は案内順に続きます。
- 衣装に配慮し歩幅小さめに。
- 玉串は打掛・袂を払って持つ。
- 写真撮影は指示に従い静粛を保つ。
- 祝拍は明るく、場を乱さない音量で。
神棚は日常の拝礼に合わせ、無理のない簡略作法で整えます。
家庭の神棚では簡略で十分。榊を新鮮に保ち、玉串は必要時のみ丁重に奉ります。
- 日々は二拝二拍手一拝で拝礼。
- 月次・年始に榊を新調。
- 紙垂は清浄に保つ。
- 迷えば氏神に相談。
玉串の準備と作り方:榊・紙垂・麻の付け方と選び方

玉串は榊に紙垂と麻や木綿を結び、根元を清浄に整えます。
玉串の基本は清浄。白い紙垂と麻・木綿を結び、結び目は目立たぬ位置に。汚れはその都度交換します。
- 紙垂は均等に配す。
- 長さは神前・玉串案に合わせる。
- 仕上げは毛羽を払って清めます。
榊は艶のある葉と傷みの少ない枝を選び、長さは神前に合わせます。
葉の照りと張りが命。枝は真っ直ぐで節が詰まったものを選び、長さは現場に合わせます。
- 目安:家庭用25〜35cm、祭場40〜60cm。
- 斜めに水切りし給水。
- 変色葉は除く。
- 棘や割れは避けます。
紙垂は白く清潔に折り、乱れたら交換して体裁を守ります。
紙垂は白無地の和紙を使用。汚れや折れ癖が出たら交換し、清浄を保ちます。
- 折り幅は均等、角は鋭角に。
- 厚手和紙で型崩れ防止。
- 端は揃えて揺れを美しく。
- 収納は平らに乾燥保管。
流派差があるため、最終判断は神社や祭式者の指示に従います。
地域・神社により作法差があります。榊・玉串の細目は執行神社の案内を最優先に。
- 例:回す方向、手順の言い回し。
- 柏手の音量・回数の差。
- 紙垂の形・結びの違い。
- 事前連絡で不安を解消。
調達・費用・玉串料:入手先・相場・のし表書きの正解

生榊は花店・神具店・ネット直送で入手でき、サイズと価格は用途次第です。
鮮度重視なら産地直送が安心。式日程に合わせ、長さと本数を事前手配しましょう。
- 入手先:花店、神具店、直販農家、EC。
- 相場:家庭用一対 数百円〜、祭場用 数千円〜(サイズ・本数で変動)。
- 直前手配は在庫確認必須。
- 定期交換は定期便が便利(神具店・EC各社のサービスを活用)。
人工榊は常設に適し、本番の神事は原則として生榊が基本です。
常設や高温期の保形に人工榊は有用。ただし正式祭儀は生榊が相応です。
- 利点:水替え不要、虫・カビに強い。
- 欠点:生気・香の欠如。
- 併用:平時は人工、祭礼は生榊。
- 表示:防炎・材質を確認。
玉串料は初穂料の一種で、金額は地域・祭儀規模・立場で決めます。
玉串料はお供えの志。個人か主催かで幅が出ます。無理のない範囲で整えます。
- 地鎮祭(施主):2万〜5万円+神饌。
- 参列者:3千〜1万円。
- 神前式:初穂料5万〜10万円目安。
- 神葬祭:5千〜3万円(地域差あり)。
のし袋・水引は場に応じて選び、「御玉串料」等を表書きしてフルネームで記します。
慶事・着工は紅白蝶結びの水引(のし有りの祝儀袋でも可)。神葬祭は黒白または双銀の結び切りで、熨斗(のし)は付けません。迷えば神社に確認を。
- 表書き:御玉串料/御初穂料/奉納。
- 弔事:御玉串料(黒白・双銀、結び切り、のし無し)。
- 名入れ:フルネーム・社名肩書併記可。
- 中袋:金額・住所・氏名を明記。
取り扱い・保管・処分:長持ちのコツと安全な納め方

日持ちは切り口の給水と涼所保管で伸び、直射日光と乾燥を避けます。
到着後は斜めに水切りし、清水に活けます。直射日光・空調直下は避け、涼所で管理。
- 水替えは毎日、器は清潔に。
- 10〜15℃の涼所が理想。
- 霧吹きで葉の保湿。
- 茎を1cmほど切り戻す。
交換の目安は葉のツヤと張りで判断し、迷ったら早めに替えます。
葉の反り、黄変、落葉が兆候。体裁が崩れる前に新しい榊へ。
- 目安:7〜14日(季節で前後)。
- 光沢が鈍れば交換。
- 枝先のしおれは合図。
- 祝祭日前に整備。
使用後の榊はお焚き上げや神社へ納め、地域の作法に従います。
祭後の榊は粗末にせず処します。可能なら神社へ相談し、地域の作法に合わせます。
- お焚き上げ:社頭で受付の有無を確認。
- 自宅処分:塩で清め紙包みの上、自治体の分別ルールに従って可燃へ。家庭での焼却は不可。
- 玉串の紙垂は外して分別。
- 供物台も拭き清めます。
カビや虫を防ぐには通風と水受け清掃を徹底し、衛生を保ちます。
湿気と汚れが原因。器のヌメリはカビの餌。通風と清掃を日課に。
- 水受けは中性洗剤で洗浄。
- 受け皿の水漏れに注意。
- 風通しを確保、壁密着を避ける。
- 生花を多種同置しない。
まとめ

迷ったら氏神や執行神社に事前確認し、榊と玉串・玉串料を早めに整えて、当日は指示に従い丁寧に奉奠しましょう。
- 日程が決まったら神社へ確認
- 榊と紙垂を準備、所作は数回の練習で十分
- 玉串料と水引の体裁を整え、当日は余裕をもって参集
参考・出典
- 神社本庁『神道いろは』(神社本庁公式サイト・刊行物)
- 神社本庁『神社祭式行事作法解説』
- 神社新報社『神社の基礎知識』
- 各神社公式「玉串奉奠の作法」ページ(例:明治神宮、出雲大社、全国の神社案内)
- 文化庁「宗教統計調査」基礎資料(用語・分類の参照)
- Wikipedia「玉串」ほか関連項目(参照時は最新版も確認のこと)